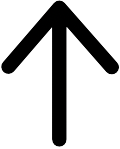ヒマラヤと岩手、どこか懐かしい風景
飯坂大 自然と寄り添う八幡平の暮らし
2023.11.17
ネパールのグレート・ヒマラヤ・トレイルを踏査する〈GHTプロジェクト〉を立ち上げ、旅の記録をトークショーなどでも発信をしている、フォトグラファーの飯坂大さん。東京を拠点に各地を飛び回っていた飯坂さんだが、縁あって2021年に岩手県八幡平市に移住した。山や自然に囲まれた暮らしも3年目を迎え、すっかり馴染んできたところだ。
「現在の住まいは津軽街道のかつての宿場町、街道沿いにある古民家です。岩手山から八幡平までの山々の連なりを一望できるロケーションがすばらしく、家の裏手には岩手山がそびえています。なにがうれしいかって、裏庭と山が地続きになっていること。以前から、自分の家がカモシカやウサギが棲む山とつながっていて、朝起きて気が向いたら山を歩いたり走ったり、そういう暮らしがいいなと思っていました。わざわざ山に出かけずとも、『山がそこにある』という贅沢を噛み締めているところです」
“採集”のための山歩き
暮らしのなかに自然があり、自然のなかに暮らしがある。山との距離が近くなったから、心理的な距離感も変化してきた。日々、自然や季節の移り変わりを身近に感じる一方で、大好きな縦走の機会は減っているとか。
「いまはアウトドアアクティビティとしての縦走よりも、生活の一部である採集に出かける機会が増えています。妻の母と一緒に山菜をとりに行ったり、酒屋のおじさんと松茸採りに出かけたり、経験者に山のことを学んでいるところ。山菜やキノコは登山道ではないところに生えているので、当然、歩くルートが異なります。歩き方が違う、目の付けどころが違う、だから難しくておもしろい。自分の目を養うと言うのでしょうか、まったく見つけられなかった山菜も、慣れてくると徐々に見つけられるようになる。これも山を知る術の一つなんだと実感しています」
山菜やキノコを探しながら獣道を行く。足場は悪い、クマも出る、道迷いの危険もはらんでいる。人の手が入っていないエリアでは、整備された登山道を歩くときよりも野生の勘を研ぎ澄ます。
「そうやって培う自分のなかの野生味と、周囲の自然の野生を擦り合わせていく作業の積み重ねが、山での暮らしなんだと思います。僕は写真家なので、そのなかに分け入って自分が感じたものを写真として切り取りますが、山での経験が増えるにつれ、景色の捉え方も変化していく。その変化を感じられるのも、こちらの暮らしの醍醐味です」
シンクロする里山の風景
岩手に移住して感じるのは、自然に生かされているという感謝が、暮らしのなかに色濃くあることだ。そこに山がある、だから感謝してその恵みをいただく。その意識は、〈GHTプロジェクト〉で見つけたヒマラヤの暮らしともどこかシンクロするという。
「昨年、コロナ禍を挟んで久々にヒマラヤに出かけることができましたが、現在暮らしている東北の風景と重なって見えました。山間の集落で、湧き水をかまどで沸かして豆腐を作っている豆腐屋のおばあちゃんの生活。山や自然の神さまに感謝を捧げるお祭りの風景、生活のなかにある信仰心。少し前の日本で当たり前に見られた営みが、ここ、東北にはわずかに残っています。そして、同じような風土や営み、文化を、ヒマラヤでも目にすることができます。標高は高いですが、グレート・ヒマラヤ・トレイルを取り巻く環境は里山ですから、そこで営まれているのはまさに里山の暮らしなんです」
たとえば、その昔、馬の一大産地だった岩手では、街道と馬は切っても切れない関係にあった。隣町に残る「チャグチャグ馬コ」という祭事では、華やかな装束に身を包んだ馬の行列が、チャグチャグと鈴をならしながら、滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡八幡宮までを練り歩く。一方、ヒマラヤの生活にもヤクやロバが欠かせない。
「動物が人やものを運んで街道を行き来するさまは実にヒマラヤらしいのですが、同時に、どこか岩手っぽくも見えるんです。また、岩手では山の中の娯楽として郷土芸能が栄えましたが、これは生活に根付いた思想や信仰から生まれたもの。一方、ヒマラヤではチベット仏教が人々の人生観や社会観に深く浸透していて、彼らの1日は祈りと共に始まり、祈りで終わります。暮らしの質が似ているのかもしれません」
グレート・ヒマラヤ・トレイルはヒマラヤの山間の村と村をつなぐ生活道なのだから、根っこにあるものは日本の街道と同じである。人や物資、文化が行き来する街道沿いの里山暮らしがシンクロするのは、不思議なことではないのかもしれない。
「奇遇ですが、現在暮らしている古民家は、街道が賑わっていた当時、旅籠として旅人を受け入れていたそうなんです。ヒマラヤを歩いて旅した自分と江戸時代の旅人の姿、過去と現在、ヒマラヤと岩手が重なり合う、不思議な縁を感じています」
いま生きている人たちの物語を次世代につなぐ
こうした岩手の暮らしは、飯坂さんの心境にも大きな変化をもたらした。20代、30代の旅で受けたもてなしや経験というギフトを、「40代になったいま、少しずつお返ししていきたいと考えるようになった。
「そう考えられるようになったのも、ローカルという意識を持てるようになったからだと思います。東京にローカル感がないとはいいませんが、少なくとも僕が暮らしていた周囲には地域内の交流はなく、自分の中でローカルというものの輪郭が定まっていませんでした。現在の暮らしには自然の恵みを交換し合い、見守り合う、そういう交流が息づいています。たとえば僕が仕事で家を空けているときなんて、僕が帰ってくる頃合いをみはからって近所の人が雪かきをしてくれ、『おかえり』と声をかけてくれる。ローカルがある日常の豊かさってこういうことなんだろうって実感しています」
飯坂さんが考えているのは、住民の姿を写真に遺し、高齢化が進んでいる地域の物語を後世につないでいくことだ。その舞台は、生活の場である古民家。ここを交流の場として開放しながら、多くの人たちの物語を紡げる場所として育てているところだ。
「自分が美しいな、価値があるなと思うものを撮りたい気持ちは変わりませんが、これからは自己表現だけでなく、周りの人たちの物語を地域で受け渡していきたい。だから、この古民家でトークショーやスライドショーを企画しています。誰かの景色や物語、消えつつある文化を次世代に渡し、その裾野を広げるお手伝いをすることが、僕なりのお返しなんです」
カメラ機材とたくさんの思い出を詰め込んで
岩手の暮らしに浸りつつも、ライフワークである〈GHTプロジェクト〉ももちろん継続中。岩手で培われた新たな生活の視点が、ヒマラヤの旅にも生きてきそうだ。
「〈GHTプロジェクト〉の中の暮らしのワンシーンとして思い出すのは、ネパールの食卓に欠かせないダルバートです。味噌汁・ごはん・副菜から成るネパール流の定食で、米飯と豆のスープ、スパイスで炒めたタルカリに、ちょっとした漬物を合わせます。〈GHTプロジェクト〉のような長い旅になると、人の気配のない区間が何日も続くことがあります。そんなときは事前に近くの村で自炊用の米と野菜を譲ってもらい、バルトロ75に入れて背負って歩くんです。
野菜はイモだったり青菜だったり、そのときどきで変わりますが、メニューは決まってダルバート。米を炊き、野菜をスパイスで炒めたら水を加えて煮込み、米飯といっしょにいただきます。村のある場所や高度によって取れる野菜が異なるので、食材の移り変わりでも旅感だったり季節の違いだったり、土地ごとの情緒を味わえるんですね。作ってもらったり、見よう見真似で自炊したりしているうちに、いつしかダルバートは〈GHTプロジェクト〉に欠かせない名脇役になりました。だから日本でトークショーや報告イベントを開催する際には、地元の食材を使ったダルバートを振る舞っているんですよ」

米に生の野菜、欠かせないスパイス。あわせて2、3kgの食材をばんばん放りこんでも、まったくへたらないバルトロ75が頼もしい、と飯坂さん。たくさんの使い古したギアと定番のカメラ機材に、季節の食材をまるごと収納したバルトロは、なんともヒマラヤらしい佇まいといえるだろう。
「タフネスが売りのバルトロは、なにも変わらないようでいて、ヒップベルトが一体型になったり、フロントポケットのメッシュ素材の強度が向上したり、少しずつアップデートされています。だからでしょうか、現地調達の食材や生活物資のような想定外のアイテムも、まるごと引き受けてくれる懐の深さのようなものを感じています。ポケットの数や大きさ、使い勝手のよさという機能面もいいけれど、この懐の深さが長い旅にはありがたいんですね」
今年は7年ぶりにマナスルのエリアを訪れる予定だ。移住して家庭をもち、生活環境も人間関係も大きく変化した飯坂さんは、7年ぶりに訪れるヒマラヤの村でなにを感じるのか。7年前に写真を撮らせてもらったローカルの人々との再会と本場のダルバートの味わいを、心待ちにしている。
Text:RYOKO KURAISHI
Photo:DAI IIZAKA